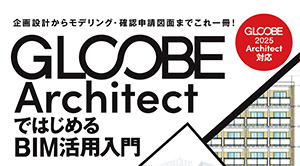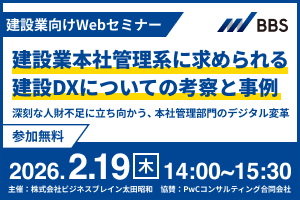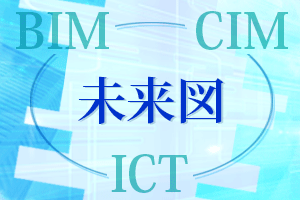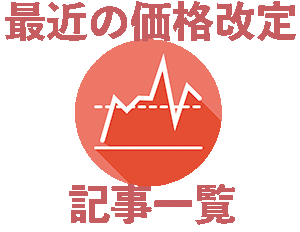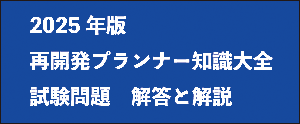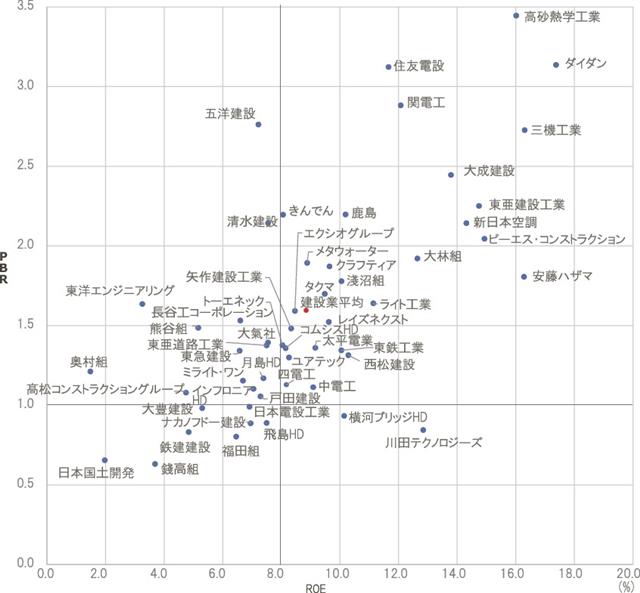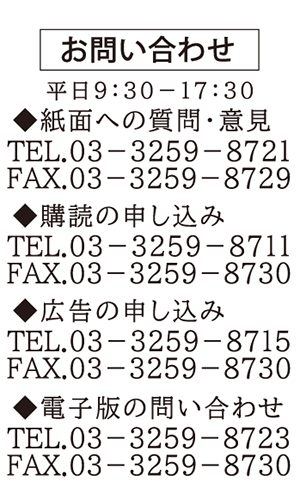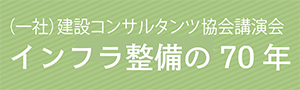改正建設業法全面施行を前に開かれた25年12月の中建審総会。賃金規制までは踏み込まないが、総会で承認された労務費の基準は事実上の建設業に対する行政指導の発動基準となる。また発注者に対しても勧告・公表が可能で、コンプライアンス重視の中、公表が抑止効果となることに期待も集まる
2026年を迎えた。国内の製造業と非製造業、大企業から中堅、中小まで業種と規模にかかわらず企業の景況感は悪くない。その中、建設産業界では25年12月12日の第3次・担い手3法全面施行を受け、「労務費の基準(標準労務費)」導入に伴う新しいルールが始まった。事実上、今年から本格運用が始まる新ルールには、発注者と受注者、重層下請け構造、材工一式見積もりなど、これまで課題として指摘されてきた産業構造と商慣習の転換を促すことへの期待もある。ただ、取り組み成果を建設業界が評価する「答え合わせ」にあまり時間の猶予がないことも事実だ。 環境好転のシグナルはいくつかある。25年12月、日本銀行が公表した「12月企業短期経済観測調査(短観)」。12月の企業の景況感を示す業況判断指数は、大企業・製造業で前期比1ポイント増のプラス15、非製造業・建設の中小企業も同4ポイント上昇のプラス22だった。
建設産業も好循環が続く。公共事業関係費は19年度から当初予算と国土強靱化予算を合わせて8兆円台の高水準を維持する一方、人材の産業間確保競争でも、24年度雇用動向調査で入職から離職を引いた数値は建設業が最大値となった。建設業界に人材が集まり始めたことになる。
民間投資を含めた建設市場も拡大が持続する。建設経済研究所と経済調査会が25年10月に公表した『建設経済モデルによる建設投資の見通し』によると、26年度名目建設投資は80兆7300億円と、80兆円の大台に乗せた。過去建設投資額が80兆円台だったのは、90年度から93年度までと96年度の5年しかない。
しかし40兆円台まで半減した市場、リーマン・ショックなどこれまで幾多の危機をくぐり抜けた中小の建設業経営者に、バブル期並みまで市場規模が拡大したことへの高揚感はない。
既にこれまでさまざまな危機を回避してきた経営者のアンテナが、先行きへの不安を感じ取っているからだ。例えば、サプライチェーン(発注者を含む生産供給網)で共有されている「担い手確保」の先行きがある。国立社会保障・人口問題研究所の『日本の将来推計人口(23年推計)』によると、日本人労働力数は生産年齢人口(15歳から64歳)が20年から35年の15年で900万人超減少する。日本の代表的業種である製造業の就業者は約1000万人だから、15年で製造業が消滅する計算だ。
この傾向は建設産業界の技能労働者数にも直結していることが、建設経済研究所の『建設経済レポート』で浮き彫りになっている。全国の技能労働者数は20年の244万7130人に対し、35年には191万9416人まで減少すると推計。毎年約3万5000人が減少し続ける中で、建設生産力・供給力を維持しなければならないことを突き付けられた格好となった。また多くの労務主体の中小規模現場では、生産性向上だけで労働力の減少をカバーすることも難しい。
外国人材については、これまでの技能実習制度に代えて、特定技能制度にひも付けた「育成就労制度」を27年度からスタートさせる。
ただこれから始まる標準労務費の導入に関連するさまざまな取り組みが評価される最初の「答え合わせ」までの時間はそう長くはない。最初の関門は4年後の「30年」だ。
新ルール「標準労務費」導入との相乗効果が期待される一つとして、「建設キャリアアップシステム(CCUS)」がある。登録数は「技能者(25年11月末で176万人)」と「事業者(同30.5万社)」の二つ。登録更新は、技能者が10年、事業者は5年ごと。技能者には直接本人に更新案内が届く。累計で技能者登録が40万人を突破したのは20年。つまり4年後には40万人の登録更新の状況が判明する。
そもそもCCUSは登録に当たって技能労働者と事業者(専門工事業)に“やらされ感”が強かったといわれる。あと5年足らずの間に、CCUSのメリットを理解してもらい更新数を一定程度確保できるかどうかは、今年から本格的に始まる新ルールの浸透とコインの裏表の関係にある。
言い換えれば、この新ルールは、産業構造転換の試金石となるだけではなく、CCUSという建設産業界のビッグデータ活用の未来をも左右することになる。
建設産業も好循環が続く。公共事業関係費は19年度から当初予算と国土強靱化予算を合わせて8兆円台の高水準を維持する一方、人材の産業間確保競争でも、24年度雇用動向調査で入職から離職を引いた数値は建設業が最大値となった。建設業界に人材が集まり始めたことになる。
民間投資を含めた建設市場も拡大が持続する。建設経済研究所と経済調査会が25年10月に公表した『建設経済モデルによる建設投資の見通し』によると、26年度名目建設投資は80兆7300億円と、80兆円の大台に乗せた。過去建設投資額が80兆円台だったのは、90年度から93年度までと96年度の5年しかない。
しかし40兆円台まで半減した市場、リーマン・ショックなどこれまで幾多の危機をくぐり抜けた中小の建設業経営者に、バブル期並みまで市場規模が拡大したことへの高揚感はない。
既にこれまでさまざまな危機を回避してきた経営者のアンテナが、先行きへの不安を感じ取っているからだ。例えば、サプライチェーン(発注者を含む生産供給網)で共有されている「担い手確保」の先行きがある。国立社会保障・人口問題研究所の『日本の将来推計人口(23年推計)』によると、日本人労働力数は生産年齢人口(15歳から64歳)が20年から35年の15年で900万人超減少する。日本の代表的業種である製造業の就業者は約1000万人だから、15年で製造業が消滅する計算だ。
この傾向は建設産業界の技能労働者数にも直結していることが、建設経済研究所の『建設経済レポート』で浮き彫りになっている。全国の技能労働者数は20年の244万7130人に対し、35年には191万9416人まで減少すると推計。毎年約3万5000人が減少し続ける中で、建設生産力・供給力を維持しなければならないことを突き付けられた格好となった。また多くの労務主体の中小規模現場では、生産性向上だけで労働力の減少をカバーすることも難しい。
外国人材については、これまでの技能実習制度に代えて、特定技能制度にひも付けた「育成就労制度」を27年度からスタートさせる。
ただこれから始まる標準労務費の導入に関連するさまざまな取り組みが評価される最初の「答え合わせ」までの時間はそう長くはない。最初の関門は4年後の「30年」だ。
新ルール「標準労務費」導入との相乗効果が期待される一つとして、「建設キャリアアップシステム(CCUS)」がある。登録数は「技能者(25年11月末で176万人)」と「事業者(同30.5万社)」の二つ。登録更新は、技能者が10年、事業者は5年ごと。技能者には直接本人に更新案内が届く。累計で技能者登録が40万人を突破したのは20年。つまり4年後には40万人の登録更新の状況が判明する。
そもそもCCUSは登録に当たって技能労働者と事業者(専門工事業)に“やらされ感”が強かったといわれる。あと5年足らずの間に、CCUSのメリットを理解してもらい更新数を一定程度確保できるかどうかは、今年から本格的に始まる新ルールの浸透とコインの裏表の関係にある。
言い換えれば、この新ルールは、産業構造転換の試金石となるだけではなく、CCUSという建設産業界のビッグデータ活用の未来をも左右することになる。