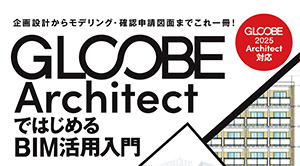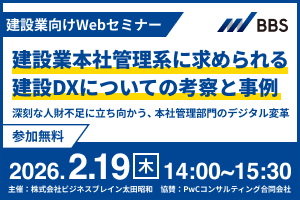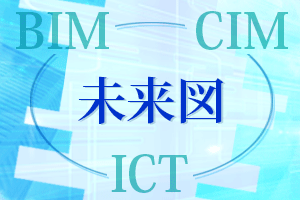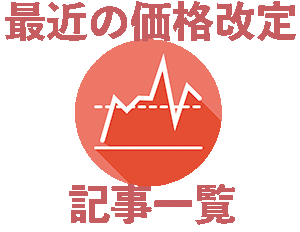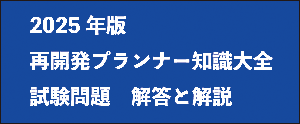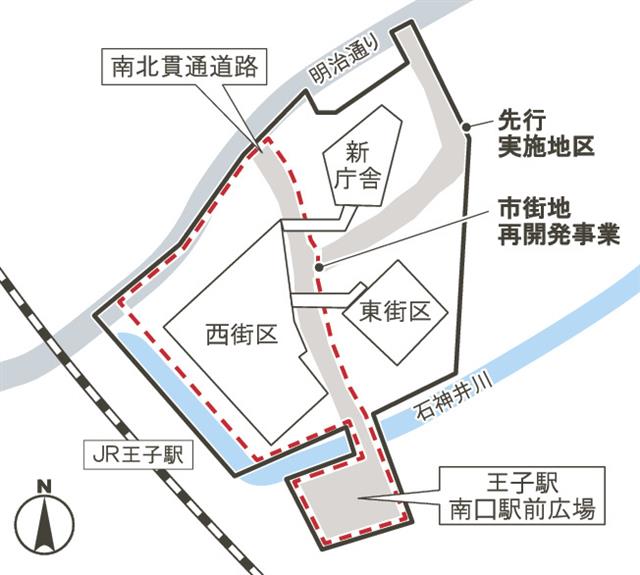1970年代から80年代にかけて、わが国では建築ドローイングの表現が大きな飛躍を見せた。実務上の要求を超えて建築家たちは多くのエネルギーをドローイングに注いだ。画面は大きくなり、技法は多様化し、ひとつの独立した作品として鑑賞されるものへと昇華していく。90年代に入りCADの普及によって衰退していったドローイングによる表現は、ポスト戦後の日本建築に何をもたらしたのか。2日に開かれたシンポジウム「建築ドローイングと日本建築1970s-1990s」では、その多義的な意味をさまざまな角度から読み解いた。
1970年代から80年代にかけて、わが国では建築ドローイングの表現が大きな飛躍を見せた。実務上の要求を超えて建築家たちは多くのエネルギーをドローイングに注いだ。画面は大きくなり、技法は多様化し、ひとつの独立した作品として鑑賞されるものへと昇華していく。90年代に入りCADの普及によって衰退していったドローイングによる表現は、ポスト戦後の日本建築に何をもたらしたのか。2日に開かれたシンポジウム「建築ドローイングと日本建築1970s-1990s」では、その多義的な意味をさまざまな角度から読み解いた。
東京都文京区の国立近現代建築資料館で開催されている展覧会「紙の上の建築 日本の建築ドローイング1970s-1990s」の関連イベントとなるシンポジウムでは、ゲストキュレーターの戸田穣金沢工大准教授の進行で住まいの図書館出版局編集長の植田実氏と歴史工学家の中谷礼仁早大教授がトークを展開した=写真。
この中で植田氏は、菊竹清訓が1960年に東京で開催された世界デザイン会議において「塔状都市」「海上都市」を収録した「METABOLISM/1960-都市への提案」を発表したことに触れ、「社会性を持ったドローイングが描かれたことはそれ以前にはなかった。1960年をもって日本の建築ドローイングが始まったのではないか」と指摘。さらに磯崎新氏の「孵化構造」(1962年)について「建築だけでなく文化の深いところで時間を考えていることに衝撃を受けた」などと振り返った。
中谷氏は「建築図面は時として芸術作品に見えることもあるが、同時に実用品であり、版下に近い。何かを生み出す元基であって、複製されることで真価が現れる」とした上で、「元基としての図面はもう描かれていない。いまの建築はこうした図面がないから弱くなっている」と指摘。特に70年代から80年代初めに描かれた建築ドローイングは「人類にとって一番大切な宝ものに必然的になっていく」と高く評価した。
また、今回の出品作品では毛綱毅●(口偏に広の旧字)の『建築古事記』を「この展覧会の白眉」と激賞。「毛綱が何をやりたかったのか、もう一度冷静に考えないといけない。ぜひ毛綱研究が進むきっかけとなってほしい」と語った。
公式ブログ
【紙の上の建築展】何かを生み出す“元基”ドローイングがもたらしたものとは 3氏が語る
[ 2017-12-13 ]