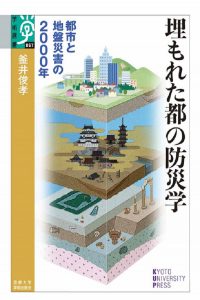
『埋もれた都の防災学 都市と地盤災害の2000年』(京都大学学術出版会 1800円+税)
著者は、「人間は自然を改造して都市を造ってきた」と語る。古代から続くローマは自然の地形の上にさまざまな遺構が積み重なっていまに至っている。「都市は自然災害などによって破壊され、また新たな都市をつくる、といった繰り返しの上に成り立っている」と続ける。いまは、アスファルトやコンクリート、構造物で覆い隠されているのでかつての姿を見ることはできない。人は崖や斜面を切り盛り土することで、なだらかな坂をつくり、道路をつくった。しかし、盛り土した部分は脆弱だ。実際、東北地方太平洋沖地震や熊本地震では、盛り土部分が大きく崩壊し、住宅をのみ込み、街を破壊した。
「地盤条件を十分考慮しなかったのが都市計画の失敗の原因」という。歴史を遡ると危険を顧みず開発した結果が災害を引き起こしているのがわかる。そもそも日本の開発は14世紀の南北朝時代から加速した。山の木を切り草を茂らせ牛馬を飼うという循環が形成された。牛馬は水田を耕す重要な動力であったことから飼料としての牧草は必要だった。その結果、日本の生産性は向上し人口が増加した。しかし山は保水力を失い、天井川が発達した。そして災害も多く発生するようになった。
ただ、江戸時代までは土地は公的財産であったことから、土地を勝手に開発することは認められず適度にバランスが取れていた。また、「江戸時代は統制が取れていたため、人は斜面地や周辺では住まなかった」というように、地滑り地などの危険個所には住まなかったため大きな災害につながらなかったというのだ。しかし、明治に移行し地租改正が施行されるやいなや状況は一変する。土地の私的所有が認められ、好きなように改変できるようになった。
著書では地盤工学の専門家の立場から、過去の地盤災害の歴史を振り返りつつ災害リスクを教えてくれる。「わたしたちの暮らす街の下はかつてどのような町でどのような災害があったのかを紐解き人間の関係を探る防災考古学」と本書を紹介する。
これからは人口減少が加速する。「だからこそ、都市のあり方を見直し、コンパクトな街に転換するべき」と訴える。
というのも現状は新たな開発が相次いで行われていて、高齢化が進み過疎化している街の隣で木を切り造成している。「開発が行われれば、災害の発生リスクが高まる」と力説するように、過去の都市づくりが証明している。
地下から掘り起こす「防災考古学」 京都大学防災研究所斜面災害研究センター教授 釜井俊孝
半分だけ倒壊したコロッセオ、大阪城の堀跡に生じた凹み、年々高さを増す天井川。これらはいずれも、“やり過ぎてしまった”開発に対する自然からの反撃である。「自然の改造は、必ず反動を生む」と筆者が語るように、地下に埋もれた災害の痕跡は、人びとがその地で自然と対峙してきた歴史を伝え、現代に続く災害リスクを教えてくれる。わたしたちの暮らす街の下には、どのような歴史が眠っているのだろうか。地盤災害と人間の関係を探る防災考古学ともいえる1冊だ。災害の歴史とともに歩んできた都市の地盤は、もはや地中に埋もれ目に見えないだけに奥が深く興味深い。



