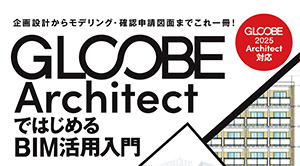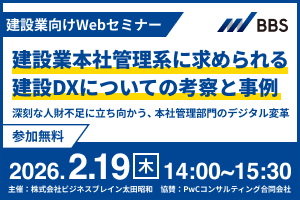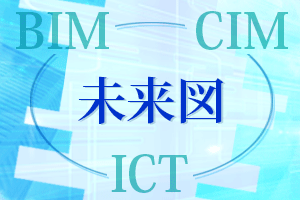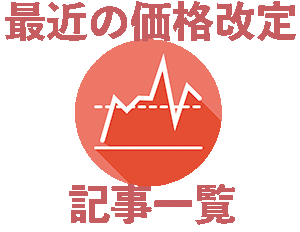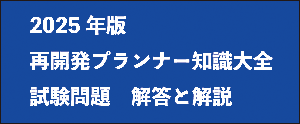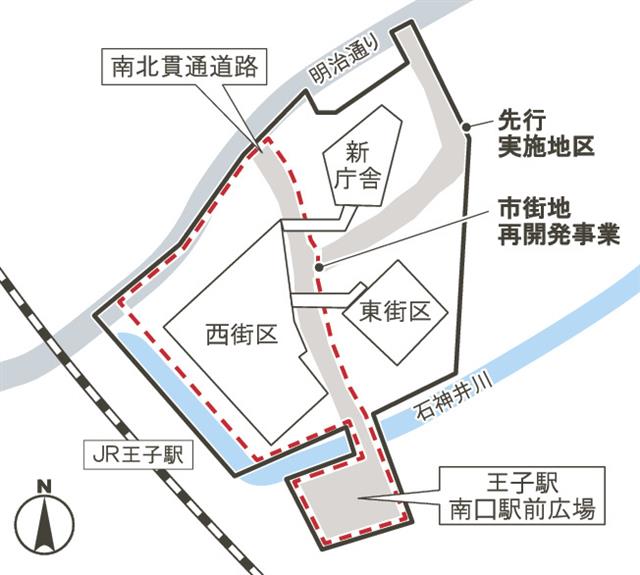1887(明治20)年から続くわが国最古の建築メディアである日本建築学会の『建築雑誌』が、いま若い世代を中心に話題を集めている。2018、19年の編集委員長を務めるのが建築家の藤村龍至氏(東京藝術大准教授・RFA主宰)だ。「学びとしての建築」を全体コンセプトに掲げながら、斬新な視点と編集によって、建築の「今」とその先を見据えた議論を喚起する誌面は大きな反響を呼び、建築雑誌を目的とした入会者は例年より倍増しているという。藤村氏に誌面づくりのポイントと今後の展開を聞いた。
初回となる18年1月号では、「学び」を通じて社会の変化に対する実態と課題を明らかにするとともに、その装置としての建築の役割を広く伝えていく姿勢を明確に示し、特に前回のオリンピック・パラリンピック東京大会開催前夜の社会情勢を照らし合わせ、その歴史に学びながら、20年以降、ポストオリンピックの日本における建築の未来を占うことを編集方針の第1に掲げた。
「より多くの読者に関心を重ねてもらおう」と、特集を第1、第2の2本立てとし、“大特集主義”を解体したことも「五十嵐委員会のレガシー」を継承したものだ。各分野の議論をリサーチし広範なトピックを扱う第1特集に対して、第2特集では萌芽的、実験的なトピックを扱う。
例えば2月号では、設計における協働のあり方を『みんなのけんちく』と題して第1特集で取り上げ、第2特集『共感の時代の専門家の社会参加』では新国立競技場や築地市場移転などが大きな社会問題となった背景としての専門家の立ち位置や振る舞いに迫った。
そこに通底するのは「長谷川逸子さんの湘南台文化センターを歴史的に位置付けるようなことをしながら、専門家の社会参加を考えるというように、常に最新の話題をその場の関心だけで解くのではなく、歴史をリファランス(参照)しながらみていく姿勢」だ。

表紙とその裏を飾る『建築漫画』も五十嵐委員会のレガシーの1つ。「そもそも開封しない人がいるのではないか」という当時からの議論を下敷きに、「袋を開けてもらう」仕掛けとして、従来の学会誌にない主題があふれ出すような工夫を凝らした斬新な表紙が毎号展開されている
複数の企画が同時進行するだけにデジタルネットワークを活用して情報を共有。会議もペーパーレスを基本に「全員パソコンを持参してGoogleドキュメント上で企画案を作成し、Slack(スラック)で全体の進行管理をしている」 という。
2年間の任期では、「前半の12カ月を、いま学会でどういうことが話題となり、どういう人がいるのかを知るためのリサーチ期間」と位置付ける。そこで学んだことをフィードバックしながら「後半の12カ月はデザインフェーズとして、学会がいまどういうことをしていくべきなのか、学会の活動そのものをデザインしていく企画書を書くようなつもりで特集していきたい」との考えを示す。「例えば建築の法律はどうあるべきか、アカデミズムは、大学とはどうあるべきか。そういう大きな問いかけをしていきたい」と。
若手会員の増強に寄与することも編集方針の1つだ。「昔は民間の建築雑誌が数多くあり、巻末には若手がいろいろ寄稿して世に出る前の予備軍というか解放区的な場所があった。それがいまは失われている」状況下にあって、若手研究者や現役の大学院生などが発言できる場を積極的に増やしているのも「学会誌の役割」だと強調する。身近でリアルな存在が誌面に載ることで学生たちにも大きな刺激を与える。なにより「文章を書くことはマニフェストする練習としてすごく大事であり、それがフィードバックされて建築家の、研究者としての自我が形成されていくことにもなる。そういう目線で将来きちんと成長してくれそうな人か、編集委員会でも人選ではかなり吟味している」と語る。
「若いデジタル世代の感覚が今後より前面に出てくることを期待している」としながらも「単に若者礼賛ではなく、ネットワークの感覚でどこまでできるのか、半分肯定的に、そしてちょっと批判的に見ていきたい」と、その先を見据える。