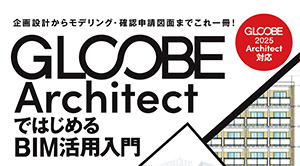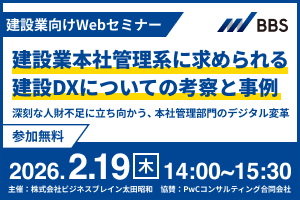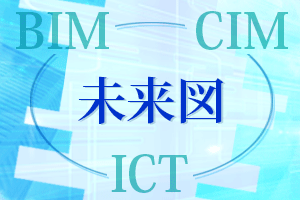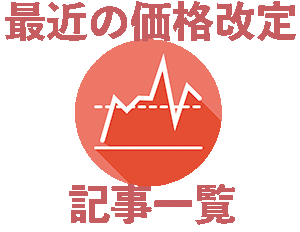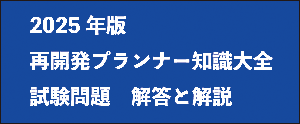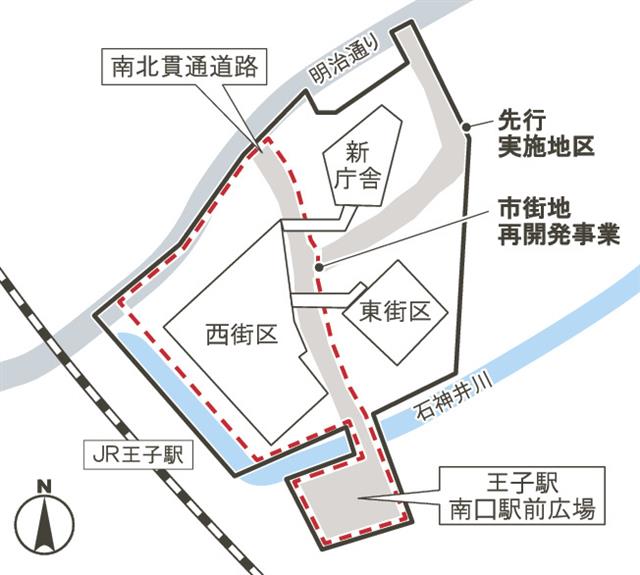初めて書いたミステリー小説が江戸川乱歩賞の最終候補になった。大分県臼杵市の豪華な館に招待された福岡市の設計事務所に務める社員が、建物に秘められた謎を解く。それも単なる館ものミステリーではなく、震災対策を見据えた建築が主役の小説といえる。
今回の小説は、東日本大震災を目の当たりにして建築的なアイデアを思いついたことがきっかけになった。論文や提案設計として具体化する手段もあったが、「物語にしたら多くの人に伝わるのではないか」と考え、館ものミステリーの中にアイデアを盛り込んだ。
「30年以上設計をやってきて、設計以外で表現、創造したかった」とも振り返る。かつて次点になった都市再生機構の団地再生デザインコンペで、設計趣旨を物語調に書いたことがあり、下地はできていた。それでも仕事をしながら書いた初めての小説は、ほぼ1年をかけて書き上げ、半年間推敲した。
母校の九州大や九州産業大で非常勤講師もしており、「建築設計を志望する学生が少なくなった。卒業設計ではスケールの大きなものが減る一方、リノベーションの設計は増えた」と実感している。「長寿命化対策も大切だが、自分の生活の範囲に閉じこもっている感じがする。大きな夢を持てない時代だけれども、もっと社会との関係性を伝える提案があってもいい」と強調する。
そのため、「若い人が建築設計に希望を持てるような内容にしたかった」。それが「今は法規上無理だが、実現する可能性はある」という震災対策の構造だ。
取り付きやすいようにユーモラスな表現も採り入れた。そのひとつが方言で、設計事務所に務める女性社員は博多弁、大分県警の刑事は大分弁を話す。大分弁は、地元建設会社の梅林建設社員に翻訳してもらった。
ミステリーによくある血なまぐさい殺人現場などはない。「悪い人を出したくなかった」という言葉に人柄がうかがえる。登場人物がどの時間にどこにいて何をしていたかという時系列やストーリーの展開に合わせた文字数の配分などは、理系出身らしくエクセル表で管理した。マンションを舞台にした次作の執筆も始めたが、「仕事が忙しくなったので今は中断中」と笑う。
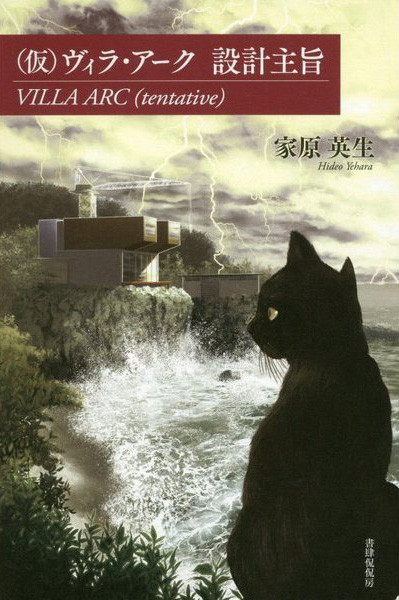
『(仮)ヴィラ・アーク設計主旨』書肆侃侃房/1500円+税
阪神・淡路大震災で兄を失った妹が、疎遠になっていた父親から自らが設計した自宅に招待される。友人が務める設計事務所の所員らとともに訪れたのは、大分県臼杵市の断崖に建つ豪華な館「ヴィラ・アーク」。消えた黒猫を捜すうちに行方不明者が相次ぎ、館もの本格ミステリーの幕が開く。
一級建築士ならではの推理で館の設計に隠された秘密を解明していき、最後に明かされる「設計主旨」は、地震大国・日本に新たな建築の構造を提案する。
建築用語や実在の建築家の作品が随所にちりばめられ、読者を建築の世界に誘う。