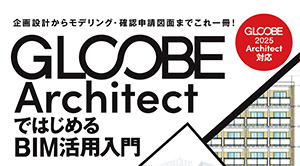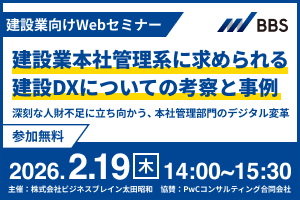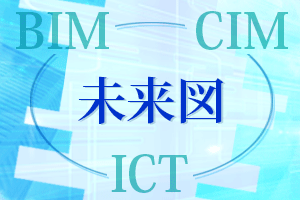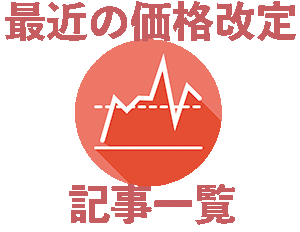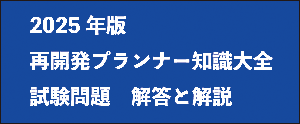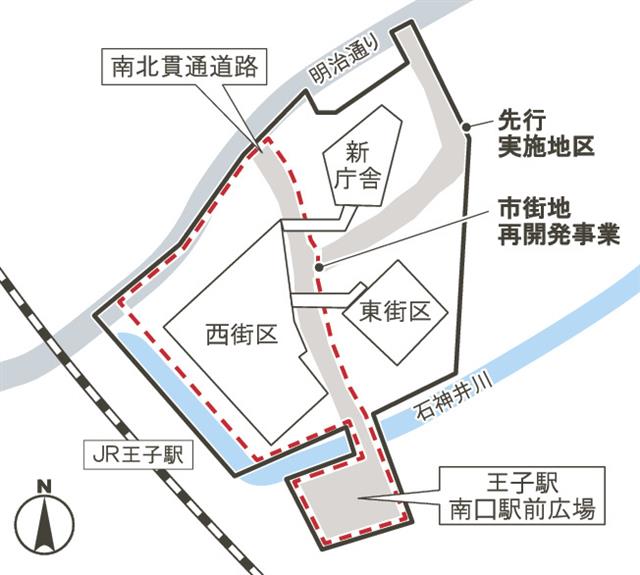近年急速な発展を続けるシンガポールでは「緑地の立体化」ともいうべき高層建築と自然の新たな共生が始まろうとしている。けん引するのは建築設計事務所WOHAの黄文森(ウォン・マン・サム)氏とリチャード・ハッセル氏だ。
「サスティナブル・デザイン」を掲げ、建築全体に樹木が生い茂る特徴的な高層建築を相次いで完成させている。アジアの最先端で自然と共生する新しい建築の姿を模索する2人に、21世紀の都市計画に求められる設計思想を聞いた。 20世紀前半、建築家のル・コルビュジエは人口が過密する近代都市を批判し、建物を高層建築に集約して空き地を確保し十分な緑地を整備する都市計画を提言した。この提案は大きな注目を集め、日本を含む多くの国々で高層建築と広場の緑地を一括で整備する計画が進んできた。
しかし、この提案はあくまで「300-600万人規模を想定した都市モデルであり、21世紀に開発が進むアジアのメガシティーには適応できない」と黄氏は指摘する。特にシンガポールのように国土の狭い地域では「巨大な高層建築で都市全体を構成していく必要がある」と断言する。もちろん、こうした巨大建築には「人間に対する圧迫感」という批判が常につきまとう。そこでWOHAでは、内部に緑地を取り入れた高層建築を設計するようになったという。「都市と自然は対立するものとされてきたが、緑地を増やす建築もあり得る」と語る。
2011年に竣工した複合施設「Oasia Hotel Downtown」では、敷地面積に対し1110%の緑地を確保した。同施設は建物の内部と屋上に植生を施したほか、外壁につる状の植物を這わせた。植物の成長に伴って姿は変わり、いずれは文字どおり緑に覆われた高層建築が実現する。「緑地を垂直方向に広げたリスが走り抜ける高層建築だ。建築と自然の対立ではなく、どちらも楽しめることを重視した」という。
コミュニティースペースの確保も巨大建築の圧迫感を減らす重要な要素だ。15年竣工の公営住宅「SkyVille」では960戸の住戸を各80戸ずつ12の「村」に分割し、各村の中心に共有の緑地を確保した。緑地にいる人間の顔が判別できるよう、どの住戸も自分の村の緑地から30m以内の範囲に配置。「住戸と緑地が視線でつながる屋外リビングとなることを期待した。高層建築の上階で暮らす住民でも庭のある暮らしはできる」と強調する。現在も多くの住民が村の緑地を利用しているが、「エネルギー消費量の低減や環境性能の高い素材は普通の人には関係ないことだ。重要なのは、そこにある緑や吹き抜ける風の心地よさ、コミュニティースペースが確保されていることだ」と語る。
シンガポールは建国以来、「ガーデン・シティー」という都市ビジョンで強力に緑化推進に取り組んできた。しかし、こうした政府の施策と新しい緑化建築の関係は「鶏と卵の議論と同じ」だと語る。政府の施策で環境に配慮した建築が生まれる一方で、環境に配慮した建築が施策に貢献してきた側面もあるからだ。そのため、WOHAが進める都市を緑化する建築は「都市の未来を構築するプロトタイプであり、世界中のどの国でも当てはまる考え方だ」と指摘する。
こうした「緑化建築」が実現できる背景には、建築設計の技術的な進歩がある。00年代前半には実現性が乏しいアンビルド建築とされたWOHAの提案だったが、ICT(情報通信技術)の発達はシミュレーションやモデリングの性能を飛躍的に高めた。また日々変化する植物を維持するためメンテナンス技術や植物の成長に耐える高強度コンクリートなどの発達も彼らのアイデアの実現を支えた。ハッセル氏は「ロマンチックと思われるかもしれないが」と前置きした上で、「データの蓄積から新しいデザインやエネルギーが生まれている。技術の発展で都市も景色のように自然に溶け込んでいくだろう」と見通す。
その極致にあるのは、彼らがマスタープランをまとめた「Self-sufficiency(自給自足)」モデルだ。巨大建築の内部で公園や畑、インフラを整備し、「食べ物、水、エネルギーを自活する」都市のように機能する建築である。一見すると夢物語のようだが、国土のほぼすべてが市街地で食料自給率の低いシンガポールにとって土地の高度利用は日本以上に重要な意味を持つ。「シンガポールの大きさで人々がともに生きていくためにも、こうしたマスタープランをいずれは実現したい」と力強く語った。
「サスティナブル・デザイン」を掲げ、建築全体に樹木が生い茂る特徴的な高層建築を相次いで完成させている。アジアの最先端で自然と共生する新しい建築の姿を模索する2人に、21世紀の都市計画に求められる設計思想を聞いた。 20世紀前半、建築家のル・コルビュジエは人口が過密する近代都市を批判し、建物を高層建築に集約して空き地を確保し十分な緑地を整備する都市計画を提言した。この提案は大きな注目を集め、日本を含む多くの国々で高層建築と広場の緑地を一括で整備する計画が進んできた。
しかし、この提案はあくまで「300-600万人規模を想定した都市モデルであり、21世紀に開発が進むアジアのメガシティーには適応できない」と黄氏は指摘する。特にシンガポールのように国土の狭い地域では「巨大な高層建築で都市全体を構成していく必要がある」と断言する。もちろん、こうした巨大建築には「人間に対する圧迫感」という批判が常につきまとう。そこでWOHAでは、内部に緑地を取り入れた高層建築を設計するようになったという。「都市と自然は対立するものとされてきたが、緑地を増やす建築もあり得る」と語る。
2011年に竣工した複合施設「Oasia Hotel Downtown」では、敷地面積に対し1110%の緑地を確保した。同施設は建物の内部と屋上に植生を施したほか、外壁につる状の植物を這わせた。植物の成長に伴って姿は変わり、いずれは文字どおり緑に覆われた高層建築が実現する。「緑地を垂直方向に広げたリスが走り抜ける高層建築だ。建築と自然の対立ではなく、どちらも楽しめることを重視した」という。
コミュニティースペースの確保も巨大建築の圧迫感を減らす重要な要素だ。15年竣工の公営住宅「SkyVille」では960戸の住戸を各80戸ずつ12の「村」に分割し、各村の中心に共有の緑地を確保した。緑地にいる人間の顔が判別できるよう、どの住戸も自分の村の緑地から30m以内の範囲に配置。「住戸と緑地が視線でつながる屋外リビングとなることを期待した。高層建築の上階で暮らす住民でも庭のある暮らしはできる」と強調する。現在も多くの住民が村の緑地を利用しているが、「エネルギー消費量の低減や環境性能の高い素材は普通の人には関係ないことだ。重要なのは、そこにある緑や吹き抜ける風の心地よさ、コミュニティースペースが確保されていることだ」と語る。
シンガポールは建国以来、「ガーデン・シティー」という都市ビジョンで強力に緑化推進に取り組んできた。しかし、こうした政府の施策と新しい緑化建築の関係は「鶏と卵の議論と同じ」だと語る。政府の施策で環境に配慮した建築が生まれる一方で、環境に配慮した建築が施策に貢献してきた側面もあるからだ。そのため、WOHAが進める都市を緑化する建築は「都市の未来を構築するプロトタイプであり、世界中のどの国でも当てはまる考え方だ」と指摘する。
こうした「緑化建築」が実現できる背景には、建築設計の技術的な進歩がある。00年代前半には実現性が乏しいアンビルド建築とされたWOHAの提案だったが、ICT(情報通信技術)の発達はシミュレーションやモデリングの性能を飛躍的に高めた。また日々変化する植物を維持するためメンテナンス技術や植物の成長に耐える高強度コンクリートなどの発達も彼らのアイデアの実現を支えた。ハッセル氏は「ロマンチックと思われるかもしれないが」と前置きした上で、「データの蓄積から新しいデザインやエネルギーが生まれている。技術の発展で都市も景色のように自然に溶け込んでいくだろう」と見通す。
その極致にあるのは、彼らがマスタープランをまとめた「Self-sufficiency(自給自足)」モデルだ。巨大建築の内部で公園や畑、インフラを整備し、「食べ物、水、エネルギーを自活する」都市のように機能する建築である。一見すると夢物語のようだが、国土のほぼすべてが市街地で食料自給率の低いシンガポールにとって土地の高度利用は日本以上に重要な意味を持つ。「シンガポールの大きさで人々がともに生きていくためにも、こうしたマスタープランをいずれは実現したい」と力強く語った。