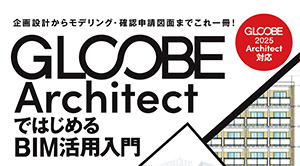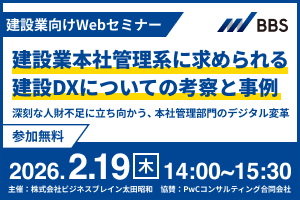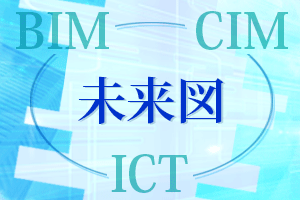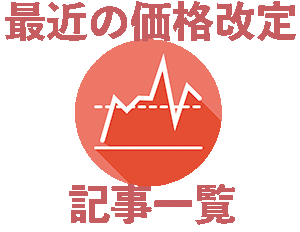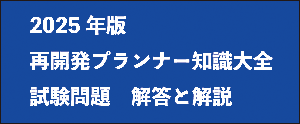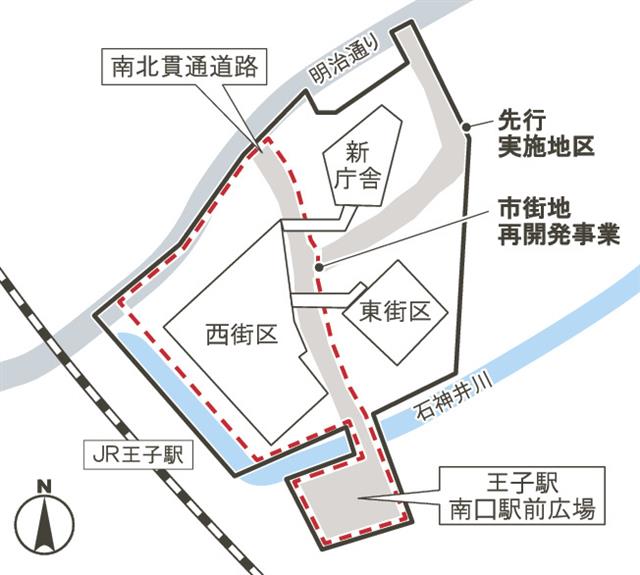建設コンサルタンツ協会は25日、連続講演会「インフラ整備70年講演会-戦後の代表的な100プロジェクト」の第14回として、「スプロールで激甚化した都市水害に挑む〈鶴見川総合治水〉」を東京都港区の政策研究大学院大学で開いた。現在では一般的になっている防災の視点でハードとソフトの対応を上流から下流までの流域で考える総合治水対策を、全国に先駆けて鶴見川で切り開いた建設省関東地方建設局(現国土交通省関東地方整備局)の京浜河川事務所の所長を務めた近藤徹氏(元水資源開発公団総裁、建設省技監、河川局長)が鶴見川の体験を踏まえ、土木技術者に対する提言を行った。

近藤氏が京浜事務所所長だった1976年9月、所管する鶴見川で越水による水害が起きた。この時、河川行政は「74年多摩川、75年石狩川、76年長良川と3年連続の破堤は、河川改修努力には限界があるという、当時の河川局長の危機感につながった」と、河川改修だけで対応することの転機を迎えつつあった。
近藤氏はその上で、「流域の都市化による水害常襲化に国も自治体も対応できなかった。だから河川中心の従来型治水から地域住民を巻き込んだ流域視点で新しい治水対策を追求した。防災は全住民が取り組むことだ」と、現在では一般的な河川改修と流域対策をセットで進める総合治水対策につながった考え方を説明した。
具体的な取り組みについては当時、近藤所長の部下として京浜事務所の調査課長だった福田昌史氏(元建設省四国地方建設局長、治水課長)、事務所で洪水予報係長だった佐藤直良氏(元国交省事務次官、河川局長)が、上流と下流の流域自治体と住民の水害・水防に対する意識の差や関係自治体などで構成した流域総合治水対策協議会の議論の内容、5年間で緊急に行った浚渫の内容と事業の仕組みなどについて説明した。
さらに、ことしの台風19号での水害抑制に貢献するなど、ラグビーワールドカップの試合会場でもある横浜国際総合競技場を中心とした鶴見川多目的遊水地事業の効果も紹介した。
また、鶴見川下流流域で育ち、現在は流域上流の東京都町田市で緑地保全活動などを続け、流域思考という考え方で知られる岸由二氏(慶大名誉教授、NPO法人鶴見川流域ネットワーキング代表理事)が、「(鶴見川水害での)総合治水効果は明らか。河川法や下水道法だけで対応はできない。流域対応が必要だ」とした上で、「ただ鬼怒川水害のような50年に一度の大雨に、いまの鶴見川は対応できない」と気候変動による豪雨多発傾向に危機感を示した。
近藤氏は福田氏らの発言を引き取る形で「想定災害レベル1、2から今後は2を超える“レベルn”も考えなければならない」とし、「気象狂暴化時代に対し、土木技術者には新たに総合土木という考え方が必要。具体的には防災アセスの制度化を提案したい」と講演を結んだ。
鶴見川 鶴見川水系は、河川法で指定された1級水系109水系のうち流域面積は106位ながら流域人口は8位と典型的な都市河川・水系。上流の町田市から川崎市、横浜市を流れる。首都圏に甚大な被害をもたらした1958年狩野川台風以降も、流域で戦後3番目の雨量だった66年台風4号で浸水戸数は1万1840戸に上った。昭和の高度成長期、スプロール化(無秩序な都市化、虫食い化)によって、上流域の町田で保水能力を維持してきた森林や農地などが急激に減少、加えて鶴見川自体が河床が浅く蛇行していたため、「年間20万m3近い土砂が堆積していた」(近藤氏)。
総合治水対策 水害防止へ河道浚渫・拡幅といった河川対策だけでなく、河川の上流から下流まで流域全体で治水対応をする考え方。そのため総合治水は、河道整備や遊水地などを柱とした河川対策と、内水排除や保水機能強化のための雨水浸透施設や下水道ポンプ場整備などの流域対策が2本柱となる。
防災アセス 地震や台風、豪雨などの災害誘因と、急傾斜地や軟弱地盤、危険物施設などの災害素因、さらに災害履歴や土地利用の変遷などを考慮し地域の災害危険性を把握する取り組み。評価結果は、地域防災計画や市民情報提供などに反映させるほか、具体的な被害想定に基づいて対策を話し合う。こうした取り組みは一部自治体で始まっているが、近藤氏の今回の提言は、土木技術者は河川や道路といった土木の縦割り意識をなくし、技術者は総合土木の視点を持って、防災アセスメントの制度化に取り組むことを求めた。
公式ブログ
【建コン協インフラ整備70年講演】河川行政経験者が語る “気象凶暴化時代”の治水対策とは
[ 2019-11-02 ]