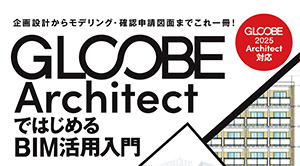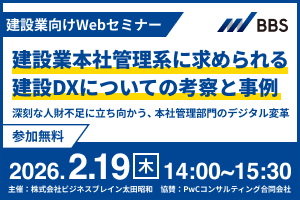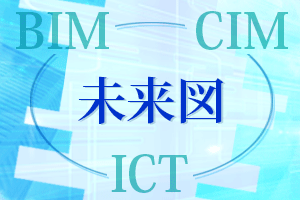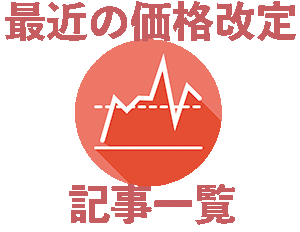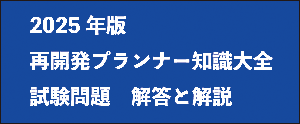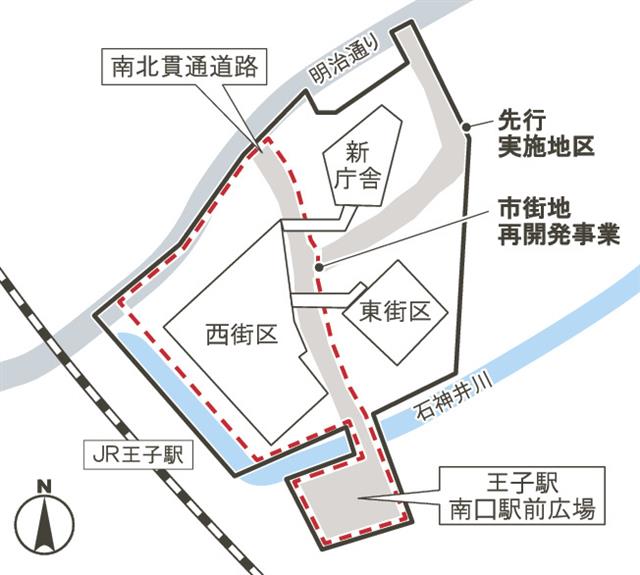建築家・藤村龍至氏(RFA主宰、東京藝大准教授)の展覧会「ちのかたち-建築的思考のプロトタイプとその応用」が9月30日まで東京都港区のTOTOギャラリー・間で開かれている。建築を「知識と形態の創造的な関係=“ちのかたち”」ととらえ、機械による計算なども伴いながら、多くの人が関わり、より良い解を目指す集合的な知をつくる方法論に発展させることで「社会のさまざまな課題解決に向けた知のツールに再定義したい」という藤村氏の世界観を表現している。
処女作に当たる『SHOP U』は、施主との対話の中からその都度問題を発見し、フィードバックさせながら設計を進めた。「最初にたどり着くべき答えがあったのではなく、模型をつくる過程で、解くべき問題がだんだんと明らかになり、クライアントとゴールを一緒に考えていく」という設計=調査を繰り返し、案の強度を高める設計スタイルのベースとなった。
東洋大で学生と取り組んだ『鶴ヶ島太陽光発電環境教育施設』は、地域に対して学生がプレゼンテーションする“パブリック・ミーティング形式”を採用した。「回を重ねるごとに生産的な雰囲気になっていった」というこの試みでは、学生10組のプレゼンと投票を繰り返した。「コンペではないプロセス案を見ながら議論を重ね、フィードバックし、当初の10案の考えを少しずつ統合することで、誰かのアイデアがどこかに残っていく仕組みができた」と集合知を生かす手法を確立。「さらに大きな数の意思からかたちをつくる」ため、あいちトリエンナーレでは、架空の庁舎を2案つくり、来場者からのアンケートをもとに毎日アイデアを進化させる手法を採った。
また、対話からの設計と比較するため、『Gチェア』では、画像検索結果から分析して類型化し、これをもとに形を整えていすを生成。『Gハウス』は、同じ手法を住宅の設計に応用している。今回の個展には、Gチェアを進化させた『ディープラーニングチェア』を出品。深層学習によっていすの形態を再構成する過程は「まるで機械とセッションしているような感覚」であり、「人機一体のコラボレーション」から、かたちを生んだ。
藤村氏は11年3月の東日本大震災以降、批評家の東浩紀氏に誘われて福島のリサーチに参加。「建築のスケールを超えた問題と向き合いながら、自分がやるべきことを模索した」と振り返る。7年通って「時系列そのものが重要だと再認識した」というのが福島県南相馬市に「仕事の工場のような建築」をつくる『小高パイオニアヴィレッジ』であり、同時に福島から西南45度に引いた軸線上には、戦後の日本が抱えてきた原発や郊外、移民、基地問題などが並ぶ“問いの軸”が浮かんだ。その軸線をさらに延長させると「今後の日本の建設産業の答え」として、インフラの輸出先となる台湾やインドネシアなどがある。「戦後70年以上にわたって反復してきたものをアジアの列島改造にフィードバックしていくのが、われわれ以降の世代に課せられた課題」と、次代を担う建築家の1人として、「線を引くことの政治性」を引き受ける覚悟をみせた。