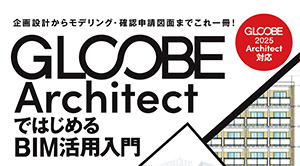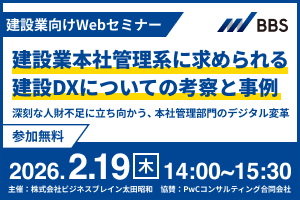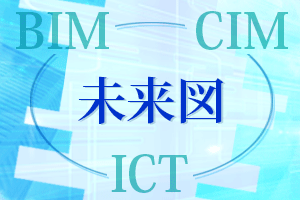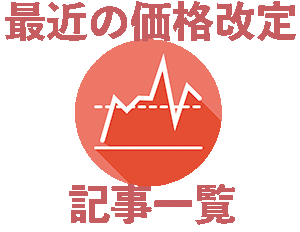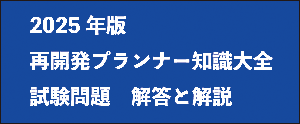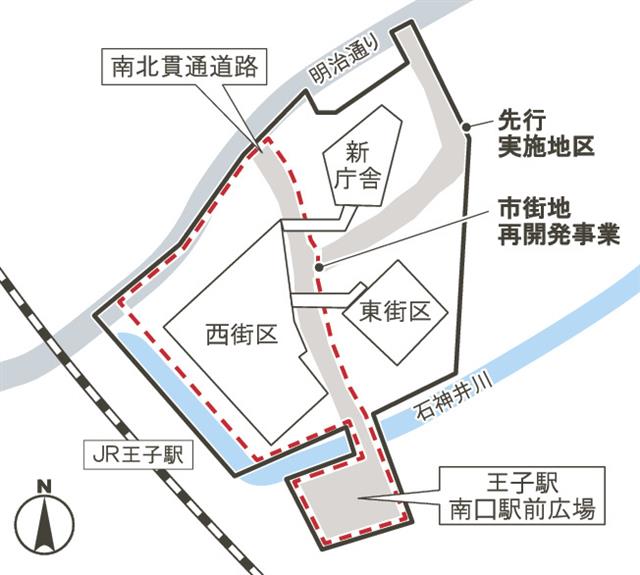フランスに拠点を置く建築家・田根剛氏(アトリエ・ツヨシ・タネ・アーキテクツ代表)の展覧会「Archaeology of the future-未来の記憶」が、TOTOギャラリー・間(東京都港区)と東京オペラシティアートギャラリー(同新宿区)で同時開催されている。これを記念した講演会では、考古学的なリサーチからアイデアを発掘・収集する設計スタイルを披瀝。「場所の記憶からつくる建築は未来の記憶となる」と語る自らの設計手法とそれに基づく作品群を紹介した。
田根氏が採用するアーキオロジーは、「一度掘り下げて、見えない文脈・文明の痕跡を考古学的に発掘し失われ、消えてしまったものと遭遇し、発見する驚きと喜びがある」というサーチ&リサーチの手法。そうしたアイデアの発掘と収集から思考と考察を始める考古学的リサーチに基づくプロジェクト群を紹介した。
さらにリーマンショックの影響でプロジェクトも2年半にわたり休止。再開後は「描いた図面が形になっていくことに感動し、建築の凄みを知った」という。現場でガラスの仕様を決める際には、実寸と異なるサンプルで即決を迫られた。こうした経験は「決断することで、いまは見えていない未来を見せるようにすることも建築家の役割だと学んだ」と、10年にわたったプロジェクトで貴重な経験の数々を振り返った。
次いで新国立競技場のファイナル11選となった『古墳スタジアム』は、仏モンペリエの事務所と組んで参加した。「大地を彫り込んだところにつくられたスタジアムの起源と、荒野に100年かけて森を築いた明治神宮外苑を手掛かり」に、都心に点在する巨大な森の中心として、古墳という象徴をデザインのモチーフとした。
エストニア国立博物館の竣工後、DGTを解散し、独立後初めてのコンペで勝ち取った『(仮称)弘前市芸術文化施設』は、明治期に酒造だった赤れんが倉庫をリノベーションするもの。「貴重な産業遺産は一度壊れてしまえば、次代につなげない」と、シードル工場に着想を得て、老朽化した屋根はシードル色に葺(ふ)き替える。れんがはPC鋼線で緊張することで、保存と耐震化を両立させる。
進行中の『10Kyoto』は、京都市街地の碁盤の目と“条”という都市を構成する要素に着目したカルチュラルファクトリーで、伝統的な町家の解体が増える中、その柱や梁を古材集成材として再利用する。『等々力のハウスインバレー』は局所的な環境の中で、さまざまな設計条件を加味し、都会でありながら自然を感じる空間をつくり上げた。
独立後、30-35人ほどのスタッフを抱え、パリを拠点に国内外でさまざまなプロジェクトが進行している。屋号につけた“アトリエ”の意味を「手を使ってものを考える。考えるよりも先に手を動かそう」と、この先の決意を表した。