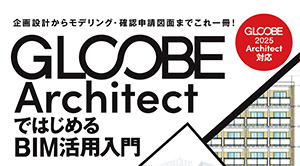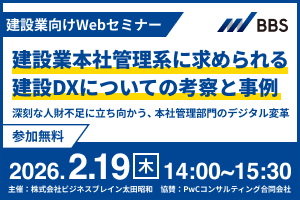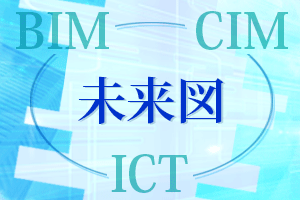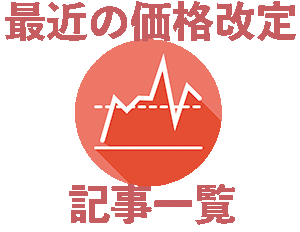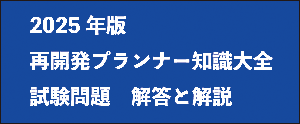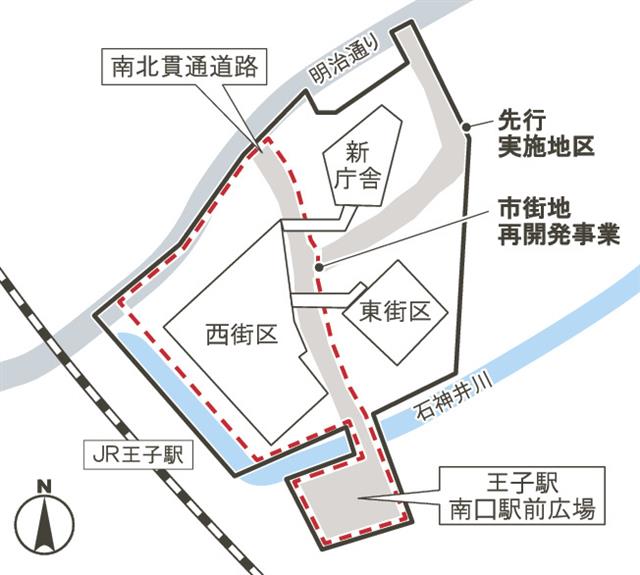東陽テクニカは、従来のマルチビーム搭載小型無人ボートに比べ、よりハイグレードな機能で港湾工事に使用可能な「TriDrone2020」(トリドローン)の開発を進めている。無人ボートで世界的実績を誇る米国のSeafloor Systems社と共同設計したモデルを4月に発売する予定だ。自動航行による省人化や時間短縮、安全性の向上を実現し、港湾工事のデジタルトランスフォーメーション(DX)に貢献する。
■自動航行で精度の良いデータを安定して取得
近年、港湾工事の従事者が減少し、水中ロボットなどを活用した無人化・自動化が進みつつある。マルチビーム測量の分野も、省人化や危険な場所での安全確保の観点から、漁船などにその都度ソナーやセンサーを艤装(ぎそう)する方式から、マルチビーム搭載型小型無人ボートによる自動航行に移行しつつある。
従来のマルチビーム測量は、船をチャーターし、船長の日程を確保した上で、ソナーや各種センサーを船体に艤装する。その際、各センサーのオフセット計測・パッチテストも行うため、調査開始までに数時間から半日程度が必要となるほか、計画測線に沿って航行するときに、船長が慣れていないと船が蛇行し、データ品質に影響することが課題となっている。
マルチビーム搭載型無人ボートの場合は、ボート、マルチビーム、各センサーなどが一体化しているため、現場に到着し、陸上のパソコンと通信を確立できればすぐに測量を開始でき、大幅な時間短縮を実現する。船は計画測線に沿って自動航行し、属人的なスキルに左右されず、安定した品質の測量データを取得できる。入り組んだところでは、コントローラーによるマニュアル操作も可能だ。
また、船体の喫水が浅いため、有人作業船が入れない極浅水域でも自動航行し、調査することができる。パソコンと無線通信し、リアルタイムで海中の様子をモニタリングすることも可能だ。
特に、港湾のICT活用工事の場合、元請けは測量会社に早く測量することを期待するため、マルチビーム搭載型小型無人ボートであればすぐ対応できるメリットがある。船長の予定を確保できなかったり、台風などで荒天待機となっても傭船費用が発生することもない。
■波高耐性のあるハイエンドタイプを開発
同社は、2016年の「EchoBoat-160」(エコボート)の発売を皮切りに、大型サイズの「EchoBoat-240」などマルチビーム測量無人ボートを継続的に販売してきた。小型とはいえ重量が50㎏以上あるため、2人以上でないと持ち運びが困難であることから、より軽量タイプの「PicoCAT-130」(ピコキャット)を20年に発売した。
昨年春に関東と九州でデモを行ったところ、機体を1人で扱えることもあり、多くの受注を獲得した。ただ、川やダムの利用を主目的とした機種のため、波への対応が難しい。湖やダムなどの内陸部でニーズがあるのだが、海で使えるモデルを提供するため、Seafloor Systems社と共同して波高耐性を持つハイエンドモデルのTriDrone2020の開発に着手した。
現在は、米国から届いた試作機が想定性能を発揮できるか検証している。修正点などを反映した上で3月までに完成させる予定だ。海洋計測部の石川隆規係長は「最大波高50cmを確保し、海の利用に耐えられるようにするとともにソナーのグレードを高め、測探点数最大1024点、周波数700kHzの超高分解能が可能だ」と特徴を挙げる。
簡単なプログラミングで使える自動航行もパッケージ化しており、事前に作成した計画測線データを自動航行用プログラムに転送すれば活用できる。さらに潮流などで計画測線から外れても、どの程度離れたらルートに戻るかなど、詳細な設定が可能だ。
また、海上保安庁の水路測量の基準が緩和されたことで、同社が提供するマルチビーム測量無人ボートは、21年から、国土交通省の港湾工事におけるICT活用工事に使用できる規格となった。
同社は販売だけでなく、トレーニングのほか、修理やメンテナンスなどのアフターサポートを行っている。発売後は、全国でデモンストレーションを予定している。
【B・C・I 未来図】ほかの記事はこちらから
建設通信新聞電子版購読をご希望の方はこちら