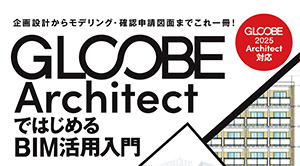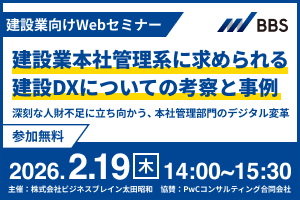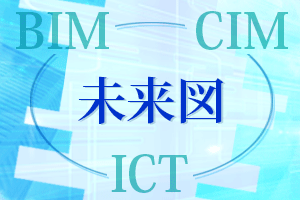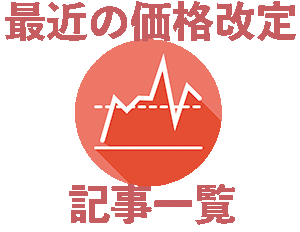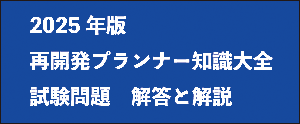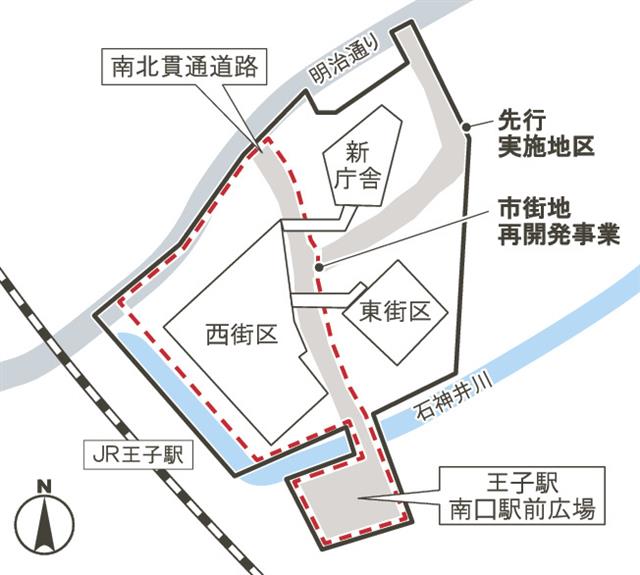戦国時代の小説といえば、武将の獅子奮迅ぶりを描くのが定石だが、本作で武将は完全に脇役だ。建設業でも職人不足による技術継承が課題となるが、今村氏は「若者が職人を志すきっかけの1つになれば」と思い、職人を主人公にした。
今村作品は登場人物の躍動感に対する評価が高いが、今回も穴太衆の末裔(まつえい)である粟田建設の粟田純徳社長への取材を通じて、職人の動きや息づかい、技を作品に吹き込んだ。源斎のモデルは、現社長の祖父に当たる人間国宝の粟田万喜三さん。匡介が石の声を聞くことができるという設定はいかにも創作であるように見えるが、「一番フィクションぽいけどリアルなところ」と今村氏は語る。実際に穴太衆には先祖代々『石の声を聞け』という教えが伝わっているという。
穴太衆では、100個の石でつくる石垣であれば100個の石を買って組み、1つも余らせずに完成させるのが究極の職人といわれる。手の感覚を研ぎ澄ますために塩で手を洗うことや、「(角に積む構造上重要な)角石まで詰めてようやく一人前」という厳しくも誇り高い教えなども作中に盛り込んだ。「積むだけでなく、石を運搬する職人もいる。あらゆる人の苦労や力が合わさって1つの建物が完成することも描きたかった。それは現代の建築現場にも通じるかもしれない」と今村氏は語る。
鉄砲の攻撃から城を守り抜く石垣の描写にもこだわった。戦の最中に現在進行形で石垣をつくることを「懸(かかり)」と言い表すのは今村氏の造語だが、そういったことは実際にあったとされる。虚実を巧みに1本の糸にする、その手腕は見事だ。
一方で、良いものをつくればつくるほど仕事が減っていくというジレンマにも触れる。「五百年で一人前。三百年で崩れれば恥。百年などは素人仕事。……己が組んだ石垣をもう一度組み直すことは生涯訪れないのだ」というのは作中でも描かれる穴太衆の教えだが、500年持つということは仕事が新規に発生しないことを意味する。さらに現代では石垣を設ける家も珍しく、城の修繕も少なくなった。「日本にある素晴らしい職人技術は、礼賛されながらも需要が減り、その結果、継ぎ手がいなくなっている。職人になりたい人を応援できる世の中でなければならない」。いまは当時と違って海外という市場がある。「近道を求めすぎるのではなく、遠回りにも活路があるのではないか」と見通す。
クライマックスでは、己の仕事に命を懸けた2人の職人が、関ヶ原の戦いの前哨戦といわれる大津城の戦いでぶつかる。「尻すぼみにならないように、攻防戦の前半は職人の“技”、後半は“心”を描いた」。「技を磨きながらも決して心を失わない」矜持を作中の職人たちに託した。
登場人物には悪人がいない。「全員が善と悪という矛盾を持っている」という。だからこそ、「蛍大名」として軽侮されがちな大津城主・京極高次も、これまでの描かれ方とはひと味もふた味も違う人間味あふれる城主として描いた。「京極高次を現代に当てはめるなら施主だろう。施主から職人に至るまで、さまざまな立場の人物を描いた。それぞれに共感できる人がいるはずなので、ぜひ手にとってもらいたい」
◆日常に遺構取り入れ 歴史を身近に感じる
歴史や時代小説で多くのヒットを飛ばす今村氏。時を経ても変わらない琵琶湖畔の景色など精妙な自然描写が本作に彩りを添える。「自宅が琵琶湖に近く、湖の描写に関しては自分を超える歴史作家はいないはずだ」と破顔する。かつては埋蔵文化財の調査員も経験した。「遺産の保存と街づくりはどちらも大切で、必ず“矛”と“楯”のような相反する意見が出る」
われわれはいかに歴史遺産と向き合い、引き継ぐべきか。「例えば、再開発の商業施設の壁面にガラス張りで遺構を展示してみてはどうか。わざわざ遺構に足を運ぶのではなく、日常的に触れ合える仕掛けをつくることで、次の世代に歴史を身近に感じてもらえると思う」
【公式ブログ】ほかの記事はこちらから
建設通信新聞電子版購読をご希望の方はこちら