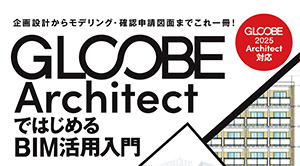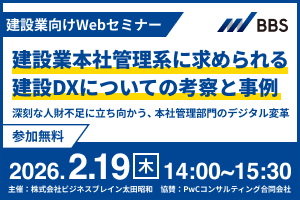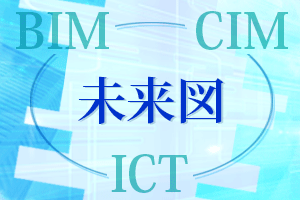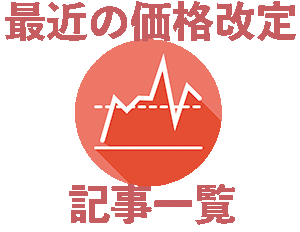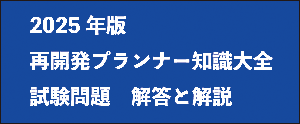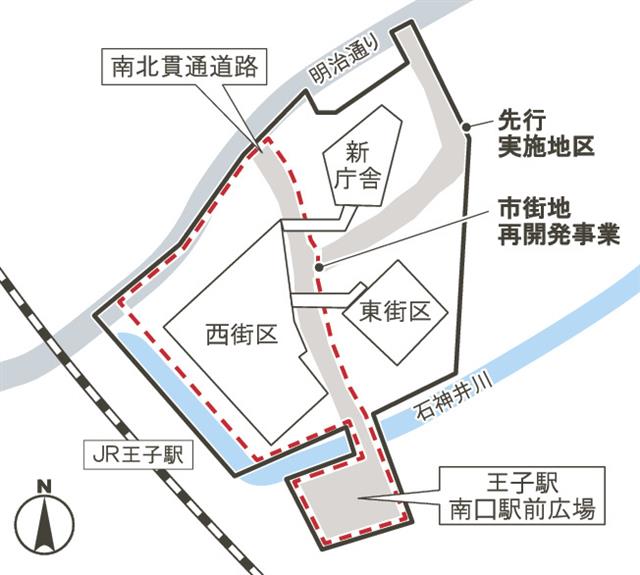【「働く場あれば住み続けてくれる」/地域維持一翼担う地元企業】
石川県能登地域の人口は、1950年をピークに減少の一途をたどっている。高度経済成長に伴う都市部への急激な人口流出が引き金となり、出生率低下につながったことなどが要因だ。
輪島市と珠洲市、穴水町、能登町からなる奥能登地区は特に顕著で、ピーク時の15万7860人(国勢調査実績)から6割以上減少し、2020年は6万1114人まで落ち込んでいる。
珠洲建設業協会長を務めるのとさく(珠洲市)の明星加守暢社長は、「『令和6年能登半島地震』を契機に人口減少がさらに加速するのでは」と危機感をあらわにする。
実際、発災直後に5人の社員が退社した。グループ全体の約1割に当たるため、大きな痛手だったが、「2次避難先で新たな就職口を見つけたと聞いた。安全な場所で家族と一緒に暮らしたいと考えるのは当然のこと」と、やむにやまれない事情を酌み取る。
この傾向は一企業に限ったことではない。石川県が実施した調査によると、3月1日現在の珠洲市の人口は、1月1日と比べて3.14%(357人)減の1万1364人で、減少幅は前年同期の4.7倍に上る。この中には自然減(死亡)が含まれるものの、生活再建に伴う転居が大半を占めるとみられ、他の市町でも同様の事態が起こっている。
また、明星社長は「2年後には多くの住民が一斉に故郷を離れる可能性がある」と見通す。それは災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与期間(原則2年以内)が関係しており、「仮設住宅に住める間は地元に残るだろう。ただ、入居期限が近づくにつれ、被災した住宅を再建するか、(市外の)別の場所で居を構えるかの選択に迫られる」との現実に直面し、「後者を選ぶ人も少なくない」からだ。
恒久的な入居が認められる公営住宅の整備を解決策の一つとして挙げるが、仮に住まいが確保されても、なりわいがなければ生活は再建できない。
同社は23、24年度と2期連続で5%の賃上げに踏み切った。民主党政権下で公共事業が削減され、ダンピング(過度な安値受注)が横行した時期と比較すれば、事業量の安定化や公共工事設計労務単価の継続的な引き上げ、受注単価の改善などで経営環境は上向きつつあるものの、「簡単な判断ではなかった」という。
それでも「社員に還元しなければならない。安心・安定して働ける場所があってこそ、住み続けてくれる。それが地域の存続につながっていく」とし、地域建設業が果たす役割が守り手や造り手にとどまらないことを改めて強調する。
地域維持に直結する担い手の入職・定着促進には、“原資”の確保が鍵を握る。今後本格化する膨大な復旧・復興工事は迅速性が求められ、「地元業者だけでは対応できない。調達力に優れた大手ゼネコンのほか、石川県建設業協会員の力が必要になる」。
そうした中で「被災地の建設企業がどう関わって(利益を出して)いくかは、業界と地域の持続性を高められる上で重要な課題」に位置付けられる。
並行して、まちづくりの在り方にも目を向けなければならない。断水状態が続く上下水道をはじめ、「当面は(インフラの)復旧が優先される。現段階で先のことまでは考えられない」ものの、「今回の地震では市全体が機能不全に陥った。一部地域のライフラインだけでも大災害に耐えられるよう事前にハード対策を講じておくことで、支援活動や避難生活への負担が軽減される」と指摘する。
鳳輪建設業協会の高木作之会長(昭和建設社長、穴水町)も人口減少の加速化を危惧しつつ、復興後の一体感醸成と活性化を見据え、コンパクトシティの推進を提案する。加えて、「震災前は奥能登の豊かな自然に魅力を感じ、移住者が増えていた」ことが創造的復興のヒントになり得るとしている。
【2024年4月5日付紙面掲載】
能登半島地震リポート
能登半島地震発災から3ヵ月-地域建設業の奮闘-(4)
[ 2024-04-08 ]