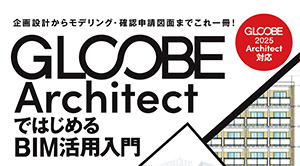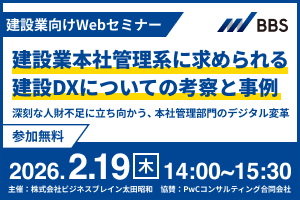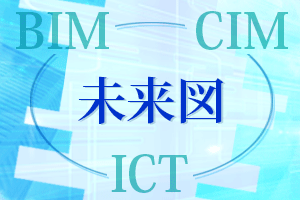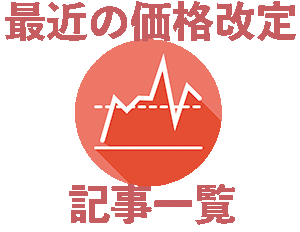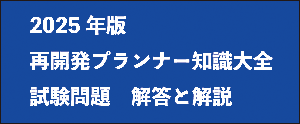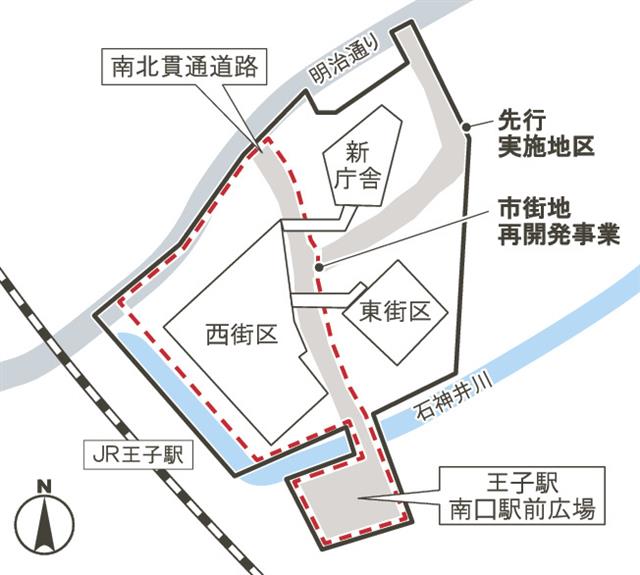【「これ、ほんとに直すのか」/復興に向けた建設業の新たな役割】
「これ、ほんとに直すのか。直せるのか。どこまで直すんだ」
「令和6年能登半島地震」の発生から間もない1月上旬、奥能登の道路啓開に駆け付けた石川県南部の建設会社社員は、大きく波打って盤面が割れ、路盤も崩落するなど延々と変状を呈している県道の現場に立ちすくみ、こう独りごちた。道路だけではない。現場への道すがら軒並み倒壊した沿道の家屋を目の当たりにし、隆起して変わり果てた海岸や漁港の現状をSNS(交流サイト)で確認して、「これまで経験した災害と何かが確実に違うと感じた」と振り返る。
石川建協の建設青年委員長で金沢建設業協会にも籍を置きBCP(事業継続計画)策定にも関わった明翫(みょうがん)組(金沢市)の明翫圭祐社長は、BCPに基づき金沢市と連携して定期的に防災訓練に取り組んできた成果を強調しつつも、「奥能登で被害があって応援に行くということはまったく想定していなかった」と話す。石川建協の平櫻保会長も県協会として今回のような広域複合災害が発生することは予測していなかったと明かす。
能登地域では17年前にも「平成19年能登半島地震」が発生したが、今回と比較して被災規模は小さく、県南部の建設関係者の間では「能登は能登、金沢は金沢と、いわば“ひとごと”という捉え方」が支配的だったといっていい。加賀建設(同)の鶴山雄一社長は「それが今回の地震災害では皆が自分ごととして感じるようになった。ひとごとじゃないからこそ、復旧・復興に向けた最適解は複雑で難しい」と指摘する。
県内の地域建設業の多くが、今回の震災で初めて自分ごととして災害の復旧・復興に向き合い始めていると言えよう。県でも復興プランづくりに着手した。単なる復旧にととめず、能登の魅力を一層高める「創造的復興」を目指すという。
しかし、全国トップ級の高齢化率に加え、急激に人口減少が進む奥能登地域で、壊滅的被害を受けたインフラ群の復旧が財政制約という難問に直面することは確実だ。今回の地震は津波や土砂災害、液状化、火災など多くの災害を引き起こす複合災害となったため、インフラの被害額と復旧に必要な投資も相当規模に膨らむと予想され、財政面から「選択と集中」が不可避となる。
ただ、能登地域に暮らす人々は古来、「地元への愛着が強く、我慢強く、結び付きも強い」と言われ、新天地での生活の再建や集約といった提案が地域で受け入れられるかは未知数だ。真柄建設(同)の真柄卓司社長は復興ビジョン策定の方向性について、私見と断った上で、「第三者がグランドデザインを描いて、それに地元(県)が手を加えていくのが丸く収まるんじゃないか」と、まちづくりにおける「分断」回避の必要性を強調する。
「選択と集中」に踏み込むにしても、連綿と紡がれてきたコミュニティーを受け継いだまちづくりデザインができれば受け入れられていくのではないかと見通すのは鶴山社長だ。自身、今回の地震に伴う大規模火災で活動の場を失っていた、1400年以上の歴史を持つという「輪島朝市」を、金沢市で「出張輪島朝市」として再開しようというプロジェクトにも関わっており、3月下旬には同社の敷地なども利用して初開催され、多くの来場者でにぎわった。鶴山氏は「地域に支えてもらっている建設業として恩返ししたかった。輪島の人たちを勇気づける事業になればうれしい」と語った。
被災地の建設会社を除き、取材した建設関係者の幾人から通奏低音のように聞こえてきた「ほんとに直すのか」というつぶやきは、建設業が地域に関わり貢献していくには工事請負だけでは社会システム的にもはや難しくなっており、逆に建設業にはこれまでになかった総合的で多層的な新たな役割が求められ始めていることを告げているのではなかろうか。
(おわり・能登半島地震取材班=阿部真莉映、綾部康一、佐藤俊之、千葉大伸、中川慎也、深澤眞歩)