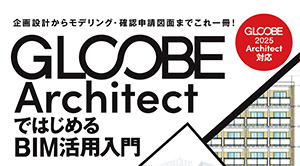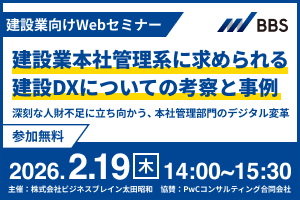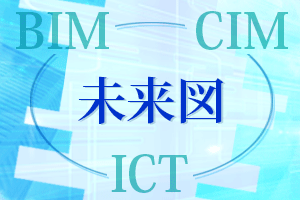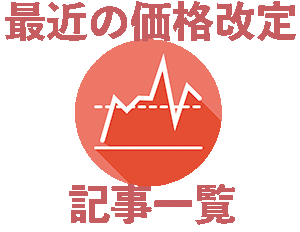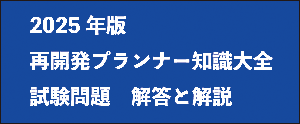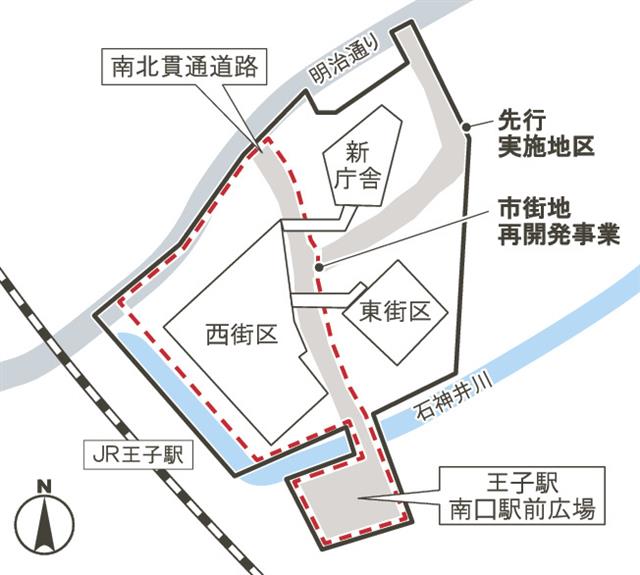【「出社してくれとは言えない」/被災者であり地域の守り手でも】
死者240人、住宅・非住宅被害13万件に上る「令和6年能登半島地震」の発生から3カ月が経過する。この震災は奥能登地域に未曽有の被害をもたらしただけでなく、災害対応の在り方や人口減少、今後のまちづくりといった地方都市が抱える課題をより鮮明にしている。地域の守り手であり、造り手でもある地域建設業は今、何に直面し、何を見据えるのか。初動対応を振り返りながら、地域再生で業界が果たすべき役割をひもとく。 「これまでに経験したことのない揺れの強さと長さだった」。珠洲建設業協会長を務める、のとさく(石川県珠洲市)の明星加守暢社長は、今回の地震をこう表現する。
震央に位置する珠洲市は甚大な被害に見舞われた。発災とともに、多くの家屋が倒壊。土砂崩れや道路損壊によって交通が遮断され、電気・ガス・水道などのライフラインも寸断した。明星社長は自身を含め、「住民は家族、親族の安全を確保することに精いっぱいだった」と振り返る。
一方、混乱の最中でも地域建設業は地域の守り手としての使命を果たさなければならない。同社は市側の要請を受け、1月4日に正院小学校の裏で発生した地すべり対策に着手。電話がつながりづらかったため、避難所を回って社員に協力を求め、7人で作業を進めた。後に分かったことだが、グループ会社の林舗道も2日から道路補修を実施していた。
グループ全体の安否確認は10日まで掛かった。幸いにも全ての社員が無事だったものの、配偶者の死去や集落の孤立などで、実際の出社は全体の7割にとどまった。緊急復旧はまったなしの状態が続き、救急・救命活動を迅速化する観点から県・市道の道路啓開が本格化していく。
のとさくをはじめ、その中心的役割を担う協会員は、夜間に必要な照明などの設備を確保できないことから、作業は日中のみに限定した。だからといって、“自らも被災者”である以上、作業後に十分な休息を取れるわけではなかった。
避難所に戻っても風呂はなく、汗や泥を流せず、満足に食事も取れない。加えて、施設内はすし詰め状態で、「3畳ほどのスペースに10人で寝ていた」(明星社長)こともあった。少しでも環境を改善しようと、現在は地元商工会議所に作業者専用の循環式シャワーを設置している。
鳳輪建設業協会の高木作之会長(昭和建設社長、石川県穴水町)が「揺れが大きく、何かにつかまっていなければ立っていられなかった。そして、まずは避難しなければならなかった」と話すように、輪島市や能登町、穴水町も同様の事態に陥っていた。
発災当日の1日は避難所で難を逃れた。2日には、いても立ってもいられず、自社へと向かった。連絡手段が途絶える中、6人ほどの社員が自主判断で出社。石川県や穴水町から要請を受けていたことから、少人数体制で道路啓開を開始した。
同協会はエリアである3市町を5地区に分けており、それぞれの地区に所属する会員で啓開作業を展開。地区間で進捗(しんちょく)や体制などを共有していた。
各社とも時間がたつにつれて職場復帰する社員が増えたため、作業人員そのものは拡大していったものの、「発災から1カ月はひたすら道路啓開を進めた。避難所からの現場通いはあまりにも過酷だった」とし、珠洲建設業協会員が置かれた境遇と酷似する。
共通点はほかにもある。明星、高木両会長は「他の経営者も同じだと思うが、奥能登住民の全てが被災者の中で、社員に対して『会社に出てきてくれ』とは言えなかった。それでも(社員が)ついてきてくれた」と口をそろえる。
その上で、明星社長は「『家族のために、地域のために』という思いをモチベーションに緊急復旧に当たっている。ただ、使命感に頼りすぎてはいけない」と指摘する。今後の収入や住まいといった生活再建を置き去りにはできず、これらを解決することが企業と地域の持続性につながっていく。
【2024年4月1日付紙面掲載】
能登半島地震リポート
能登半島地震発災から3ヵ月-地域建設業の奮闘-(1)
[ 2024-04-08 ]