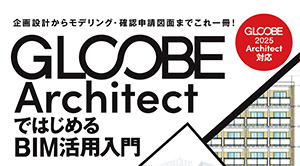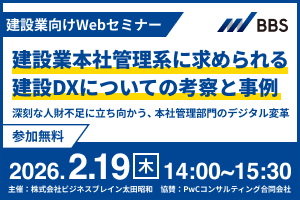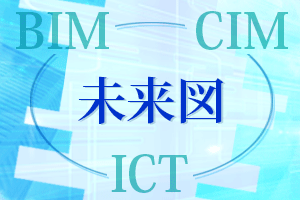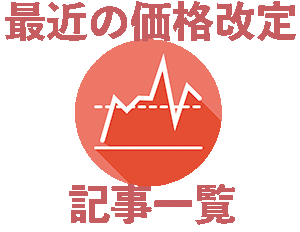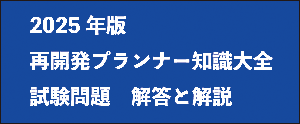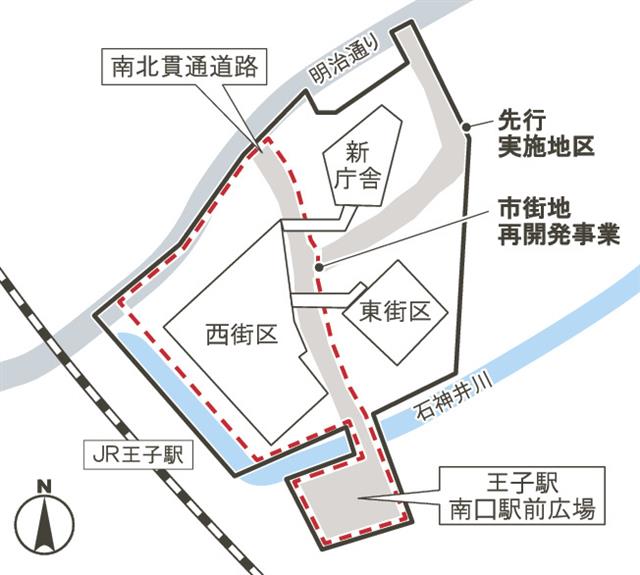日本建築美術工芸協会(aaca、岡本賢会長)の情報文化委員会は、東京都台東区の東京藝術大学でaaca30周年事業座談会「東京の過密都市空間に“市中の山居”をつくることは可能だろうか-土木・ランドスケープ・建築・アートからのアプローチ」を開いた。建築家の内藤廣東大名誉教授とランドスケープアーキテクトの三谷徹千葉大教授(オンサイト計画設計事務所)、同委員会委員長で美術家の坂上直哉氏の3人が、それぞれの立場からまちづくりへの関わり方やアプローチのあり方などを語った。
都心の中でも大規模な都市開発が常に進行する渋谷区の渋谷駅中心地区まちづくり調整会議で副座長を務める内藤氏は、「超高層ビルは好きではないが、まちのためになることで戦うのが自分の役割だ」と語り、現在の状況について「バブル期に似た楽観的な考えが支配しており、あまりに無神経だ」と警鐘を鳴らしながら、「地上階周辺はまちのものとして開かれるべきだが、そこは利益を生む場所でもあり、主戦場となっている。超高層ビルの地表面をうまくつくることが再開発を成功に導く」との考えを示した。
内藤氏は、「3.11以降、人の居場所、身の置き所を強く考えるようになった」とも述懐。スピード感が求められる復興の現場では、インフラの復旧・整備が最優先された結果として、「本来はどれも人が生きていくための空間に結びつくもの」である都市、建築、アートが段階的かつ分業的に積み上げられていく中で、「東日本大震災からの復興の現場には自分も建築家として呼ばれてはいない」と、全体を統合すべき建築家が排除され、さまざまな分野が縦割りで進められたことを課題として挙げた。
三谷氏は、敷地を支配するような作品ではなく、対話する作品をつくる「アースワーク」の概念を紹介するとともに、「直線的なエンジニアリングの考えと、反すうをもとにするデザインは全く異なる考え方だが、ものづくりの現場では同時にあることが望ましい」などと持論を展開した。
また、「アーティストが風景をつくる場から置き去りにされている」と坂上氏が危機感を示し、積極的にまちをつくる立場としてデザイナーや職人とともに、建築家やランドスケープアーキテクトとプロセスを共有する道筋を探るべきと提言したのに対して、三谷氏は、越後妻有トリエンナーレの仕掛け人である北川フラム氏を引き合いに、「日本にはイベントをつくるアーティストがいない。話ができる若いアーティストの存在が、こうした状況を変えていく可能性を秘めている」と期待を寄せた。
内藤氏は、これまでの自作におけるアーティストとの関わり方を振り返りながら、「技術的な部分を定着させるためにエンジニアリングも必要だ」と指摘しつつ、「戦前は美しさを内在している人がエンジニアだったが、戦後は技術的な部分を学んだ人が早く安く造ろうとした。美意識の欠如が今日の問題の根底にある」と語った。さらに「2003年に美しい国づくり政策大綱が策定されたものの、自然災害からの復興を始め、さまざまな場面でその精神は生かされていない」と語気を強めた。
三谷氏も「復興の場面でランドスケープアーキテクトは最後の最後に呼ばれる。それを変えていくことが必要だ」と同調しつつ、「土木でも時間を費やしてゆっくりとつくったものは間違いない」とも指摘した。
これには内藤氏も「建築側も土木を理解しようと努力することは必要だった」とした上で、「アーティストはわれわれが理解できない深いものを提示してくれる。一方でアートが公共空間に出てくるためには、そのエリアの都市計画などをアーティストも学ぶ必要があるのではないか」と、分野や領域を超えて相互に理解を深めることの重要性を改めて訴えた。